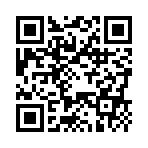2016年05月30日
自作ウッドラック
最近良くキャンプ場で見かけるアイアンラック
がむっちゃかっこいい
あれを見てから
オシャレな棚が欲しくなって
前回、色々なタイプを妄想しましたが
さんざん妄想の挙句、
やっぱり同じタイプに回帰しちゃいました

早速ですが
念願の ウッドラック 完成しました。(ウッドウェルフ?)

材料は
天板:杉材 厚み21mm
骨組み:ヒノキ
ユニフレームfan5dxが簡単に入るくらいの
大きさにしてみました。
参考:鹿番長ラックの全高は580mm
三段目を付けようか迷いましたが
低い所が使いづらい様に思えて
あえてつけませんでした。

今回はなるべく接合部に強度を出したかったので
面倒ですが、組込み式のホゾ加工に挑戦です。
というのも、隣の市のホームセンターに
最近、念願の工作室が出来たんですよ♪
これはうれしい!
電動工具ひとつ100円
壁にかかっている一般工具はタダ
時間制限なし
夢のようです♪
早速トリマーでホゾ加工してきました♪
普通の工具も
我が家のノコギリよりよく切れるのに驚きです。
これをノミで加工するのは大変ですもんね

それでも、途中で1日終わってました

メインの杉の300mm幅の天板
木目が大きく主張してる物を選んでみました
後は自宅で天板も合わせて
シャコシャコヤスリがけ~
塗料は、
天板:ワトコオイル(ミディアムウォルナット)
骨組み:ワトコオイル(ナッチュラル)
塗りはどちらも今回ムラにならない様に、
速く塗れそうな家庭用スポンジを使ってみました


最後の方、ワトコ(ミディアムウォルナット)が無くなってしまって
ナチュラル色で薄めたから色が薄くなっちゃいましたが
色に高級感が出て
いい色に染まりました
ホワイトウッドの場合は
ヤニがあるからか色ムラが出るそうなので
杉板をチョイスして正解でした♪
プラス
仕上げのブライワックス(ブラウン)がいい仕事してくれます。
木目の表情にツヤが出ていい感じ



初め、杉板が全部、反り返ってて隙間が合わず
仮組でホボ足が垂直でした
生まれたての小鹿状態・・・・(笑)
こんだけ反ってました(^_^;)
う~~ん
どうしようかと思いましたが

思い切ってホームセンターで半分に切ったら、
うまく収まりました♪(〃´o`)=3ヨカッタ

天板は
長さ:1100mmと1200mm
幅300mm
足は角27mm



小さいラックの方はクーラーボックスを置こうかと思って
作りましたが、明らかに高いですね
ジャグ用にしようか・・・
ジャグ持ってないしぃぃ・・・
それと、もうちょっと削って足を斜め角度を大きめにした方が良さそうです

短いバージョンの二段状態
天板長さ600mmと700mm



自作って面倒だけど楽しい

キャンプ場に早く持っていきたいなぁ
楽しみ~♪
2016年05月29日
おんたけ銀河村の帰り
おんたけ銀河村
いい加減しつこい?(笑)
5/5 3日目の朝
















いい加減しつこい?(笑)
5/5 3日目の朝

本日の朝ごはんは簡単で美味しい。
豚角煮のパックに温泉卵のせ

OUTは早めの10:00
管理が徹底されてそうなので、
食ったら、もうぼちぼち撤収
子供は男二人でよかったw

管理人さんから子供の日のプレゼントのおかし進呈♪
チョビットお話しした後、銀河村とはお別れです。
今回は、またまた楽しかった♪
おんたけ銀河村キャンプ場、いい所でした
また、遊びに行きたいです♪

お客さん満員では無かったですが
結構な県外から来られてる方が多かったですね
静かでしたが濃ゆい客層だった?w


地元は終わっちゃいましたが、
流石の信州
帰路の所々、桜が満開です。

帰りは、
開田高原の木曽馬の里に観光です。



やさしそうなお馬さん

家族全員で餌を集めて
わしわし、草を食べて頂いて貰きました。
食べる方も夢中ですが、集める方も夢中ですw
テレビ取材を受けて撮影してもらいましたが
恐らくボツ動画なんだろうなw
今まで登山・観光と何度か取材を受けてますが
間違いなく一度も採用されていないと思う・・・

馬だけだと物足りなく
旧飛騨街道を歩いてきました。
すまーーーん

二日連続だと流石にヒンシュクでした(^_^;)
それでも文句いいつつ
付き合ってくれる家族に感謝


最終日の汗は
帰りのルートを変えて上高地経由で
長野県松本市奈川の
「富喜の湯」
でサッパリ♪


洗い場のない露天風呂と
洗い場のある内風呂が別々になってる温泉
秘湯の感じがしていいお風呂でした。
内湯のタイルが懐かしいタイル張りで和みます。
この後は、
前から気になってた
上高地の沢渡駐車場を偵察
まさか次のキャンプに繋がるとは・・・この時はノープランでした
最後に平湯大滝を覗いて滝で〆

この大滝、冬は凍りついて、
タルマの森としてライトアップが見事ですので
是非見に行きたいスポットです。


これにて
今回のキャンプは終了
楽しいGWとなりました♪
2016年05月28日
おんたけ古道遊歩
記事投稿に取りかかるつもりが
色んな方のブログを見てたら
見入ってしまって、気付けば徘徊
GW後半、

























色んな方のブログを見てたら
見入ってしまって、気付けば徘徊
そして1日終了・・・
そんな毎日繰り返し
やっつけですが
おんたけ銀河村キャンプ場の続きです。
そんな毎日繰り返し
やっつけですが
おんたけ銀河村キャンプ場の続きです。
GW後半、
1日目の強風は低気圧を越えれば、
お天気は回復、何とかなるさ
と臨んだ二日目の5/4
道具が濡れないようにと低く設置したタープは
一晩しっかり持ちこたえてくれました。
景色は最高♪

青空だけど時折の強風は昨晩と変わらず・・・
タープを立ち上げたら、時折の突風でペグが一本
すっ飛んでいきました
危ない危ない


今日のご飯は簡単に
フランクフルトの冷凍パイ包み
チーズ入れたかったけど嫁にケチられた(^_^;)シュフハシビア
味は
アメリカンドッグ風で、なかなか面白かったです。

こんなもんで当然足りる訳もなく
非常食投入

本日はキャンプ場の駐車場からの滝巡り

車で簡単に行けちゃいますが
今年のファミリー登山の為、
体をちょっとでも動かしとこー♪

御嶽山
噴火で怖いですが
斜面がなだらかに見えますし
これなら家族で登れそう・・・に見える
今度連泊で来れたら
登ってみたいですね


御岳信仰の霊場の石碑がたくさん


1時間ほどで、
目的地「清滝」に到着♪
実際見ると、なかなか迫力あります


続きまして、新滝





古道遊歩
我が家に丁度いいコースでした
のんびりテクテク、
こんな時間の使い方が我が家にあってる。
キャンプ場からの滝巡り
約2時間半のコースでした。
次は
夜ごはんを買いに行かねば・・・
大型スーパーイオンまで30km道のりは結構遠い(^_^;)
遅めの昼食は道の駅「木曽市場」にて
山菜蕎麦
素朴で、なかなかおしい♪
お風呂は「せせらぎの四季」
茶色の鉄泉で、ほのかにいい香り❤
お昼でもお客さんが一杯でなるほどの人気風呂でした
戻ってくれば、もう結構いい時間

本日は蒸し料理がメインとハンバーグのホイル焼きで
蒸し料理もなかなか侮れません。



今晩も、時折の突風

こうやっていつまでも家族でキャンプを楽しみたい。
空は、
銀河村と言われるだけあって
いつもより大きく見える
満天の星

撮れたつもりが、
ピントがあってないオイラ(^_^;)ジブンラシイ
2016年05月26日
自作棚妄想中・・・
う~~ん
自作棚が欲しくて、妄想がいろいろ膨らんでいます(^_^;)
悩みまくってます




やっぱ作ってみたら、ガタガタして不安定なんだろうなぁ・・・・
結局のところ
良く見る
これが一番シンプルで作り易そうですので
やっぱこれかなぁ

ぼちぼち挑戦してみます。
2016年05月21日
2016年05月13日
GWはおんたけ
5月3・4・5日
GW真っただ中の登山翌日
嫁も珍しく連休体制
せっかくの連休、どっか遠出がしたいー!!
にも関わらず・・・
GW真っただ中の登山翌日
嫁も珍しく連休体制
せっかくの連休、どっか遠出がしたいー!!

にも関わらず・・・
じつは
















前日になってもキャンプ場が決まってませんでした

東か西かも決まっていない

だって何処もかしこも
キャンプ場満員御礼なんだもん・・・
まだ、営業していないキャンプ場も沢山あるから
良さげな所は尚、殺到するんでしょうね
そりゃ、殺到するにキマっとるわな(^_^;)
期待してた道院キャンプ場もまだ営業されてませんでしたし
アテが外れました
なにより
不安要素は、雨より強風・・・
浅い考えですが
内陸部の林間なら大丈夫じゃないか?
と二日前から探しまくってました・・・
それで何とか見つけた
長野県木曽郡王滝村の
おんたけ銀河村キャンプ場に漂着

標高は1400m
白樺に囲まれたフィールドと
雪をかぶった御嶽山
当日の飛び込みにもかかわらず
最高のキャンプ場でした(*^_^*)

日によっては氷点下まで気温が下がる事があるそうですが
連泊中は、そこまで冷え込む事は無かったです。
なによりこの眺望と
GW中にも関わらず空いてて良かった♪
料金は
一泊2000円/1テント
+入場料300円/一人
+タープ500円/一張
----------------------
ファミリー4人で3700円
ゴミ捨て場あり(分別必要)
テントはスノコに張るべきに見えますが
開けたところに張ってもいいそうです
(夏季には、幾つかのスノコには常設テントが張られるそうです)

オートサイトではないので
荷物はリアカーの出番(笑)

我が家は2往復でコンプリート
ちゅうか・・・
のんさん筋肉痛で真っすぐ歩けない状態でした



サイトが窪地になってるので
風を、ある程度遮ってくれる反面
坂は、ど根性!!
星飛雄馬になれますよ~

空気を読んだのか
子供たちは協力的で大活躍でした♪
ちなみに
上の建物が管理棟です
バックパックでキャンプされてるソロの方もちらほら居ました


スタッフの方は親切ですし
遊具の貸出や傘の貸し出しが
うれしい心づかいです





炊事場


トイレ


きっちり綺麗に管理されてました

初日の夜は雨と強風に遭いそうでしたので
張り綱を強めに、
相手がスノコなので
テンションをどうかけるか解らず四苦八苦しました。
天気がまだ安定している間に
チャッチャと済ましてしまう算段で
早めのご飯
本日はノーマルに焼き肉。
もしかして料理できないカモ・・・と、
カップラーも非常食として用意しときました

時折、上の方は強風のゴーーッっと大きな音がしてましたが
下の方は音の割には安定してましたので
焚火も出来ました。
時折、風向きが変わった時に起こる突風
雨もぱらついてきた所で
本日は終了

ヘキサタープのメインポールを何本か抜いて
なるべく低くして強風対策と道具の濡れ対策
夜は天気予報通り大雨になりました。
こういう時ってスノコは足元が汚れないので結構いいもんです。
夜中はごおおおおーーっとえらい音がずーーっとしてて
波の音が聞こえるキャンプ場に来てるようでした

音はすれども、突風でテントがバタバタ
したのは数度ほど
うまい具合にキャンプ場が決めれて良かった
と思えた初日でした

2016年05月10日
富士写ヶ岳
靴屋さんに修理してもらった
愛用の登山靴のソールが
またまた、取れてしまいました
一度剥がれてしまうと、
そんなに持たないもんなんでしょうか・・・
もう諦めて
新しい登山靴を新調しました
チョイスしたのはモンベルの
テナヤブーツ


靴ひもが、スノーボードでお馴染みのワイヤー式になっているので
ツマミをカチカチと回せば締まるし、
緩める場合はツマミ引くのみのワンタッチ
脱ぎ履きが簡単です♪
つまみが2つあるので
締まりの調整もしっくりきます(^-^)
登山中にワイヤーが切れてしまったら
靴ひもを通せば関節部まで対応できるそうです。
登山靴は靴底の厚みがあるので
地面の冷気をある程度ガードしてくれるから
これまで通り 冬キャンでも活躍してくれないかなぁと期待してます
冬キャンでも活躍してくれないかなぁと期待してます
 冬キャンでも活躍してくれないかなぁと期待してます
冬キャンでも活躍してくれないかなぁと期待してます5月1日朝から遅くまで田植えを何とか済ませて
早速足ならしに・・・いやいや鞭打ってますw
靴ならしに
5月2日 石川県と福井県の県境にある
田植え時期、シャクナゲで有名な
「富士写ヶ岳」に行って来ました。
富士写ヶ岳は日本百名山で有名な深田久弥さんが
小学校の遠足で初めて登った山で
登山に興味を持つきっかけになった山だそうです。
子供たちは学校だし、本日はソロ。
大内コースで火燈古道から反時計回り


今回は珍しく
朝6:30スタートです。

火燈山方向の登山口が良くわからなくてちょっと迷いましたが
舗装された道路を上に歩いて行くと発見出来ました

入口の白山神社で参拝しつつ
花が多くて、早速足止まっちゃいました(笑)

登っていくと、早速間違えそうな登山道
直進は寅ロープが張ってありますが
本道だと思って乗り越えて行きそうです


ここは木の赤い目印に沿って左折です
下調べしておいて良かった


登ってすぐ、既にいい景色

山頂からの眺望が楽しみです。

こちらから登る人は少ないのか道幅は狭い

ロープに頼らなくても登れる程度の斜面ですが
結構多かった

ふーっ 登ってるって実感できます
登ってるって実感できます
 登ってるって実感できます
登ってるって実感できます今年は雪が少ないので
開花が例年より早いようで
もしかしたら、もうシャクナゲ枯れちゃってるんでは?と心配してましたが
出合えて安堵(*^_^*)

登っていくに従って
シャクナゲが元気に山道を彩ってました
可愛い花です

富士写ヶ岳はあれかな~


一つ目のピーク
火燈山まで あと20分

新しい靴、下り坂でも
しっかり地面を捕まえてくれて
いい感じです。

8:16
ほぼ休憩なしで、一つ目のピーク
火燈山(803m)に到着。
ここで
富士写ヶ岳経由の時計回りコースっぽい
初めて登山者に会いました。
あなた・・・速すぎです(^_^;)
度々思いますが
明らかに毛質の違う人って
山にはわんさか居るんです 歳関係なくない?
歳関係なくない?
 歳関係なくない?
歳関係なくない?このまま、
まだ行けそうだし次行ってみよー



自分はもっぱら よたよた歩き
中間のピーク小倉谷山はあれかな~


春の山は花が多くて楽しいです

所々にある、シャクナゲが元気



アップダウンを繰り返し
何人かの登山者とすれ違いつつ
8:52
小倉谷山910.6mに到着

ここから富士写ヶ岳まで2時間
まだまだ
道のりは長い


それにしてもシャクナゲが見事
残すはあっちの富士写ヶ岳(942m)
がんばってこ~♪
あそこまでの標高差は
僅か32mですが
ここからが一番きつかった(^_^;)


ぜぇぜぇ・・・

解り辛い写真ですが結構な下りの斜面
早速コケました。
これを登るのきつそうだなぁ・・・
それにしても、どんどん標高を下げていきます。
標高差は200mくらいありそうです。
下りの次は、当然登りです
絶壁はなくて助かりましたが、
「延々と続く坂が続くよ~」とアドバイスされ
よろよろ~ さらに亀ペース(xぺx;)
ホントに延々と坂です

だましのピークっぽい所になんかだまされないぞ
と勝手に落胆してたら
いきなり頂上が現れました。
10:31
富士写ヶ岳(943m)
やったぁ着いたぁ♪
登山口からの標高差は720m
累積標高差は1130mでした

小倉谷山から2時間の看板から
おおよそ1時間30分ちょい
案外ペースは大丈夫だったみたい

既にたくさんのご飯タイムの方々
やっぱ人気の山です。
看板の彼方に
小大日山、大日山、
その奥にでーんと存在感のある積雪中の白山
期待通り眺望の良い山頂です

ノンアルコールビールでグビッっとお疲れさん♪

定番のカップラーとんこつ味+梅おにぎりぶっこみで
猫まんまラーメン
九州でこの取り合わせに出合ってからハマってます♪

11:15 大内方面へ下山開始

大内コースの最後のピークもなかなかの急坂です
一山下った所にあるシャクナゲが一番見所がありました。

やっぱ下山が一番足にきます。

12:16
ふらふらになりながら、登山口に無事到着
こちらのコースもなかなかきつそうです

周回で9kmのコースでした



熱くて疲れて
キンキンに冷えた川に思わずサブン。
靴を気軽に脱げるってやっぱイイ♪

さーて
帰ったらたけのこ掘りが待ってる(^_^;)
この翌日えらい筋肉痛になりました

2016年05月07日
医王の里キャンプ場つづき
この前のキャンプでは
黒いギャング(カラス)に食材をごっそり
やられちゃいましたが
2016/04/28
今週は、白い方に吠えられちゃいました(T_T)
ショックで真っ青になりましたが
免許証も真っ青になっちゃいましたヨ、トホホ
当然、自分が悪いんですが、
GWは特に要注意ですね
知り合いに取り締まりで張ってる所を
行きと帰り往復で2回切符を獲られたっていう
伝説を持ってる人が居たりします
聞く方は笑い話ですが、本人かなりショックだったろうなぁ・・・w
医王の里オートキャンプ場の方まだ
中途半端ですので続きます
オートサイトの方は何組か居ましたが
この日のテントサイト利用は
我が家の貸し切り
焚火を堪能したかったので
管理の方にお願いして
サイトの電灯は消灯して戴き
のんびりさせて頂きました。




端材の棒で
とんとん♪
曲の当て合いや
セッションをして遊んだ夜でした。
キャンプっていいねぇ♪
----------------------------
翌朝は一年ぶりの
たけのこ丼♪
(具材は餃子の具風です)

カラスには見向きもされなかったタケノコしたが
しっかり美味しい一品です。
鯉の餌は100円で一袋
一袋でも量が多めにあります。










たまごがプルンプルン♪


医王の里キャンプ場
しっかり堪能させて頂きました♪
この後
キャンプ場を後に、さらに山側へドライブ

医王山(白兀山)の登山口を通り過ぎ
更に奥に行くとイオックスアローザスキー場の頂上に出ました

キャンプ場は、
道路に囲まれたあの辺なのかなぁ?
眺望もなかなかよさそうですが
2016年は道路補修工事の為
営業はされていない様です。
ここにも登山口がありました
行先は片道0.8kmの奥医王山939m
手ごろに行けそうでしたので
今年一発目のファミリープチ登山いってみよ~♪

登山道はしっかり整備されてて
歩き易かったです。
歩き易かったです。


お馴染みの、イワウチワとタムシバ


さくっと登頂♪
この日の眺望はガスってイマイチでした。



運動の後の温泉は
地元民チョイスで
大桑おんま温泉 楽ちんの湯
ここのお湯はコーヒー色でぬるめですが
しっかり温まります。
気持ちが良くて、
テレビの前の露天風呂でまどろんで居る方がちらほら
お勧めの温泉です。


本日の〆は前々から気になってた
野々市市のシェクープル
たまごがプルンプルン♪
オムライス万歳 また行きまーす♪
また行きまーす♪
 また行きまーす♪
また行きまーす♪2016年05月04日
なう
GW後半戦
田植えも、なんとか済ませて
風が弱そうな所‥と
御嶽山が見えるキャンプ場に来ています

たるまなさんすんませーん
田植えも、なんとか済ませて
風が弱そうな所‥と
御嶽山が見えるキャンプ場に来ています

たるまなさんすんませーん
Posted by のんさん at
09:37
│Comments(2)